崇神天皇と疫病と大田田根子
第10代崇神天皇の5年というから、長浜浩明さんの計算だと西暦209年頃、奈良盆地では人口の半数が死亡する疫病が蔓延したという。
天皇は八十万の神々を集めて原因を占い、大和国の「大物主神」を敬い祀ればいいと言われたものの、祭祀の方法が分からない。すると天皇の夢に当のオオモノヌシが現れて、「私の子」である「大田田根子(おおたたねこ)」に私を祀らせればよい、と告げてきた。
天皇が大田田根子を探させると、当時は河内国に含まれた「茅渟(ちぬ)県」の「陶(すえ)邑」で発見された。
天皇は、大田田根子を大和に呼び寄せるとオオモノヌシを祀る神主とし、さらに八十万の神々を祭り、「天社・国社および神地・神戸」を定めたところ、二年以上続いた疫病はようやく終息したのだった。
日本書紀によれば、大田田根子は「三輪君」の始祖。
「オオ」は「大きい」、「タタ」は「祟り」、「ネコ」は尊称なので、「祟りを鎮める能力を持った偉大な人物」という意味だそうだ(『古代豪族と大神氏』鈴木正信)。

大物主神はなぜ祟りをなしたのか
このオオモノヌシのエピソードは、日本書紀の「神代(神話)」に2本載せられている。ただし、どちらも「本文」ではなく、参考文の「一書(あるふみ)」なので、関連する氏族の「家記」がネタ元かも知れない。
一本目では、オオモノヌシは大己貴神(=オオクニヌシ)の前に海を照らして現れると、自分は大己貴神の「幸魂奇魂(瑞祥と神霊の魂)」で、「日本国の三諸山」に住みたいと言ってきた。
大己貴神は神宮を三諸山(三輪山)に造営してその神を住まわせ、これが「大三輪の神」で「甘茂君」「大三輪君」の祖だと説明される。
二本目は、大己貴神が「国譲り」に応じて幽冥界に退去したあとの世界で、「経津主(ふつぬし)神」の地上平定に際して、帰順してきた二柱の神の片方としてオオモノヌシが登場する(もう一柱は事代主神)。
フツヌシに天まで連行されたオオモノヌシは、皇祖「高皇産霊(たかみむすび)尊」に娘の「三穂津姫命」を娶されると、八十万の神を率いての皇孫の守護を命じられている。

これらの一書では、一本目では大己貴神と大物主神は「同一神」、二本目では全く別々の神だというんだから、困ったことにぜんぜん整合性が取れてないわけだが、ぼく個人は二神は別々の神だと思っている。
上代日本文学を専門にされている松本直樹さんによれば、オオモノヌシの「モノ」とは「正体不明の超自然的な存在体を漠然と指す言葉」で、たとえばある共同体にとっては「カミ」でも、別の共同体からみれば「モノ(またはオニ)」だったりするケースがあるそうだ。
オオモノヌシについては「まさしくモノを代表する名であるが、モノでありながら、同時にカミでもあるというのは実に不可解」だとして、だからこそ「モノの正体を把握して、それを祭ることのできる人物が必要だった」と書かれている(『神話で読み解く古代日本』)。
つまりは、崇神天皇にとって大物主神は「モノ」なので、その祭り方がぜんぜん分からなかったということだろう。

この点は、いわゆる欠史八代の「宮都」の歴史が、理解を助けてくれるような気がする。正室(皇后)の実家と合わせて、列挙してみればこう。
・初代神武天皇 橿原市/鴨氏
・2代綏靖天皇 御所市/鴨氏
・3代安寧天皇 橿原市/鴨氏
・4代懿徳天皇 橿原市/皇族
・5代孝昭天皇 御所市/尾張氏
・6代孝安天皇 御所市/皇族
・7代孝霊天皇 田原本町/磯城県主
・8代孝元天皇 橿原市/物部氏
・9代開化天皇 奈良市/物部氏
・10代崇神天皇 桜井市/皇族
宮都が置かれた「御所(ごせ)市」は、もともと「事代主神」を奉じる「鴨氏」が土着していた”葛城”エリアの現在地で、6代までの天皇は、橿原から葛城にかけてが勢力基盤の地だったようだ。
それが7代孝霊天皇のとき「磯城(しき)」の県主の娘を正室(皇后)にして、宮都も「磯城」に移している。言うまでもないが、その「磯城」で700年続いた弥生ムラが「唐古・鍵遺跡」だ。
そして9代開化天皇のとき、宮都は「春日」(奈良市)に移る。そこら辺を地盤にしていたのが「和珥氏」で、開化天皇と和珥氏の皇妃(側室)の間には「彦坐王(ひこいます)」が生まれている。
というかんじで9代までの皇室は、その勢力を奈良盆地の南西部(橿原・葛城)から北東部(春日)にまで拡げていたが、今イチその支配が及んでいなかったのが三輪山に近い南東部で、10代崇神天皇はその3年(208年頃)、いよいよ満を持して桜井市に進出した———ってとこなんだろう。
その当時の桜井市にあった拠点集落が「纒向(まきむく)遺跡」。考古学者の石野博信さんによれば、そのスタートは西暦180年頃だという。
「纒向」の繁栄と「唐古・鍵」の衰退はクロスフェードするらしいので、纒向は9代開化天皇(在位177−207)の頃に開発が始まり、その息子・崇神天皇(在位207−241)から実際に運用されたってかんじだろうか。

で、そうして崇神天皇が桜井市に宮都を移すやいなや、三輪山の神・オオモノヌシが子孫による祭祀を望んで祟りをなした———という流れから考えると、どうやらその時点では大物主神を祀るべき「三輪氏」は、祖地である三輪山麓には住んでいなかった、ってことになりそうだ。
もともとは神代紀の一書にあるように、三輪氏(大物主神)も同族の鴨氏(事代主神)と同時期に、皇軍の先兵・物部氏(経津主神)に降伏・帰順したのだろう。
しかし欠史八代のどこかで、皇室に大和から追放されたか、あるいは皇室を見限って大和を退去したか、その経緯は不明だが、結果としてオオモノヌシは自分を祀る神主を失っていたし、大田田根子は一山越えた河内に住んでいたのだろう。
ちなみに歴史学者の岡田精司さんによれば、三輪氏や鴨氏の「君」というカバネは、かつては皇室に匹敵した勢力、または皇室を出自とする勢力に与えられた称号だそうだ(宗像君や上毛野君など)。

崇神天皇と纒向遺跡
ところで奈良の考古学者・坂靖さんによると、(崇神天皇が桜井市に宮都を置いていた)3世紀前半の纒向遺跡はまだ目を見張るほどの規模ではなくて、全部でざっと100haほどだったそうだ(唐古・鍵は40ha強)。
んで実は、その頃の畿内最大の弥生遺跡は大田田根子が暮らしていた河内にあったようで、坂さんが「中田遺跡群」と総称すべきといわれる河内のムラムラを一つのクニとして考えた場合、その面積は纒向遺跡の3倍以上の350haにも及ぶのだという。
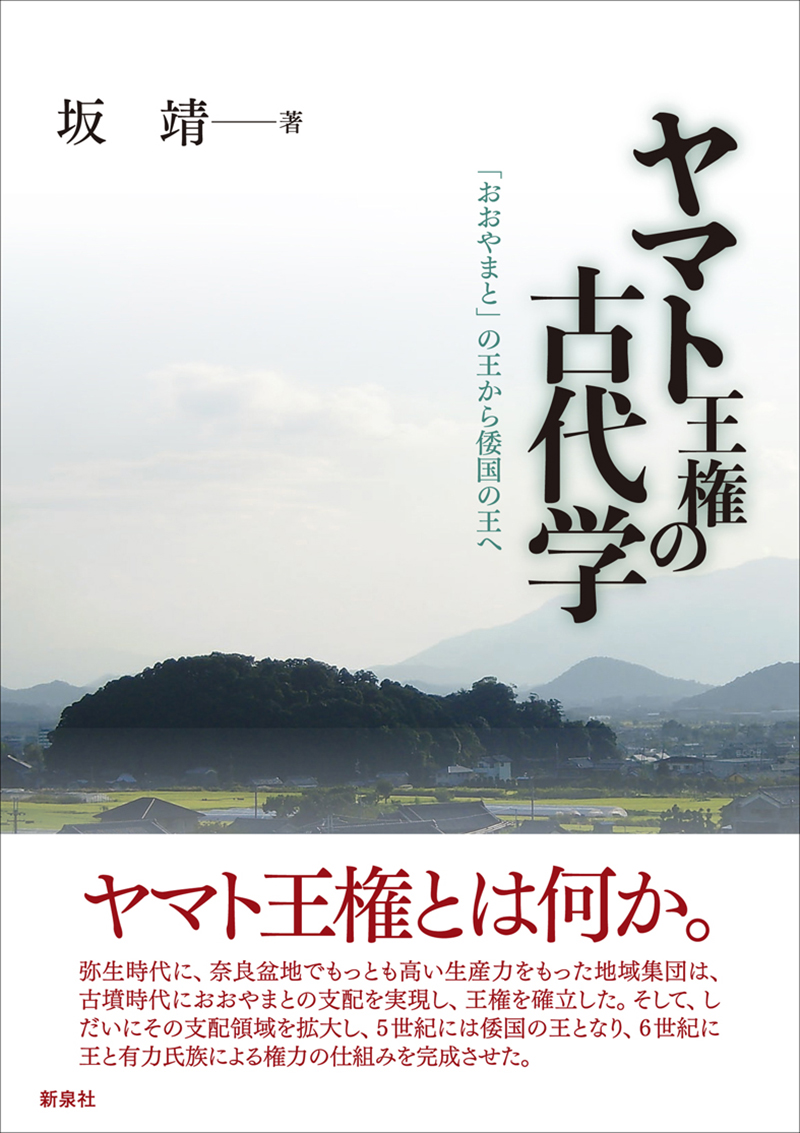
吉備との関係を示す「特殊器台」なども出土しているし、朝鮮半島系の土器も多い。河内オリジナルの土器の広がりからは、大和とは連動しない、別の勢力の存在が考えられるという。「王」の居館跡かと思われる「方形区画」の面積は約1380㎡で、この時期の纒向の約1500㎡に引けを取っていない・・・。
———纒向遺跡は、むかしから邪馬台国の卑弥呼の宮都だといわれてきたが、その3倍以上の規模をもつ河内の「中田遺跡群」は、果たして魏志倭人伝の何というクニに比定すればいいんだろう。これは結構、難しい問題では?
ちなみに日本書紀によれば、第8代孝元天皇(在位148−177)は「河内の青玉繋(あおたまかけ)」の娘を皇妃に娶っていて、その当時の河内に、皇室の政略結婚のお相手にふさわしい勢力があったことを記している。
なお、その妃が産んだ皇子、「武埴安彦(たけはにやすひこ)」は「四道将軍」の留守を狙ってクーデターを起こしたものの、崇神天皇が派遣した和珥氏の将軍「彦国葺(ひこくにふく)」によって射殺されている。

”奈良のオオクニヌシ”の祭り
さて、ここで話をアタマまで戻すと、蔓延する疫病への対策として崇神天皇が打った手に、宮中で祀っていた「天照大神」と「倭大国魂」の二柱を外に出して、別々に祀るというものがあった。
現在、倭大国魂(やまとおおくにたま)を祀っている「大和(おおやまと)神社」に伝わる『大倭神社註進状』なる古文書によると、二神は孝昭天皇元年(AD17年頃)から、宮中で天皇による直接の祭祀を受けていたのだという(『大和の古社』乾健治)。
それが崇神6年からは200年ぶりに皇居から出され、別々の場所で別々の「皇女」に祀られることになったというわけだ。
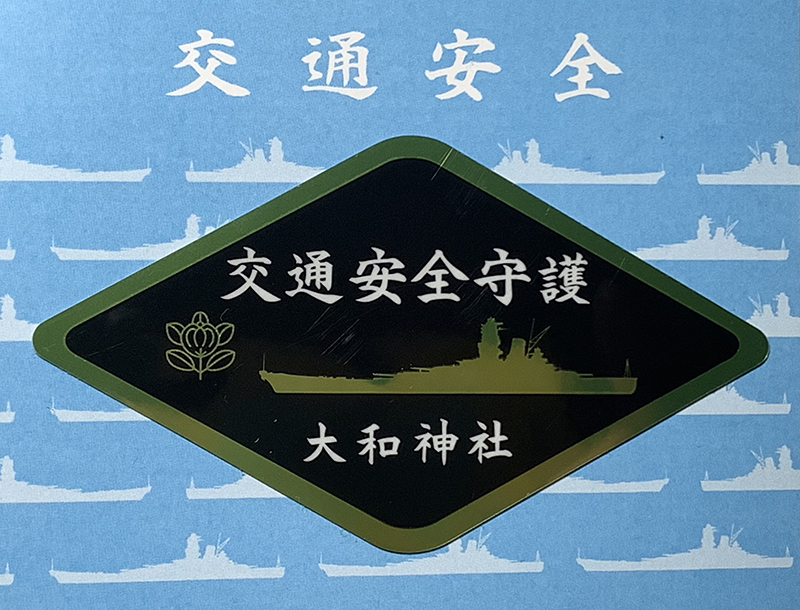
ところがこのとき、倭大国魂を担当した皇女「渟名城(ぬなき)入姫命」は髪が抜け落ち、体もやせ細って、祭主を続けるのが難しい状態になってしまったという。
そこに助け舟を出してきたのが例のオオモノヌシで、自分には大田田根子を!という一方で、倭大国魂には「市磯長尾市(いちしのながおち)」を神主にすればよい、と助言してきた。
どうやら奈良盆地の土着の神「倭の国魂の神」も、縁もゆかりもない皇女の祭祀を受けることには、強い拒否反応を示したようだ。
日本書紀によれば、倭大国魂の神主を命じられた「市磯長尾市」という人物は「倭直(やまとのあたい)の祖」だといい、その始祖は神武東征で軍功を上げて、初代の「倭国造」に任じられた「椎根津彦(珍彦)」だという。
そのシイネツヒコ自身は大分県あたりの海人族だったようだが、その一族が「倭国造」を世襲して早280年。田舎者も4代住めば”江戸っ子”だというが、長尾市もすっかり奈良盆地の土着民として認められていたということか。

問題はアマテラス
こうして疫病騒動にまつわる二柱の神主が決まり、奈良盆地には平和が戻ってきた。
が、戻らぬ神が一柱いて、それが倭大国魂と一緒に宮中から出され、大和の「笠縫邑」で皇女「豊鍬(とよすき)入姫命」の祭祀を受けていた「天照大神」だ。
この「天照大神」は、ここから実に40年以上も「笠縫邑」に置かれたまま、ついに皇居に戻されることもなく、伊勢に遷座させられた。
もちろん、この「天照大神」は、ぼくらが知る皇祖神「天照坐皇大御神(あまてらしますすめおおみかみ)」とは別の神だろう。皇祖神ではないからこそ、この「天照大神」は第14代仲哀天皇を、平気で祟り殺すことができた。
そして崇神紀の疫病騒動の意味を考えるなら、この「天照大神」は伊勢の地で、伊勢の土着民に祀られるべき神だったのだろう。ただ、200年を超える皇居での祭祀のうちに、その正体がまったく分からなくなっていた。それで「天照大神」の本来の鎮座地を探すべく、皇女ヤマトヒメの旅が始まるわけだが・・・。
それはまだ先のはなし。
崇神天皇(2)へつづく





