 邪馬台国
邪馬台国 (7)伊都国の三大王墓と三つの謎 〜三種の神器・ヒメヒコ制・倭国王帥升・女王墓〜
「倭国」連合の盟主とされる邪馬台国にとって、もっとも重要な構成員が「伊都国」だろう。そこは帯方郡の使者が宿泊する場所であり、邪馬台国が派遣する統率者「一大率」が常駐して、諸国を取り締まる場所でもある。魏志倭人伝によれば、伊都国は代々「王」が...
 邪馬台国
邪馬台国  邪馬台国
邪馬台国  邪馬台国
邪馬台国 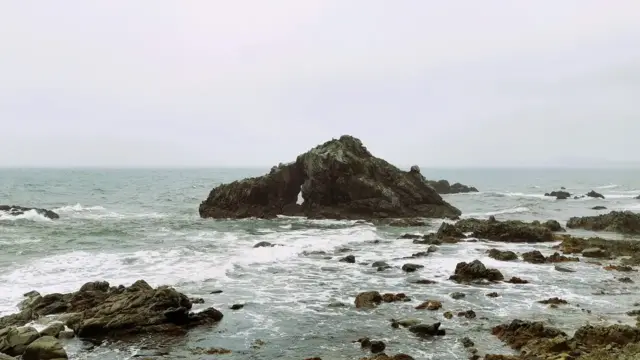 邪馬台国
邪馬台国  邪馬台国
邪馬台国  邪馬台国
邪馬台国  邪馬台国
邪馬台国  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇