日向神話とは
出雲のオオクニヌシから地上世界(葦原中国)の支配権を「譲られた」天孫ニニギは、降臨すると山の神(大山祇神)の娘・カシツヒメを娶って山の支配権を獲得した。
カシツヒメは「火中出産」で隼人の祖(海幸彦)、皇室の祖(山幸彦)、尾張連の祖(火明命)の三兄弟を産み、隼人と皇室の血統が接続された(尾張連についてはこちらを)。
成長した山幸彦は、海幸彦に借りたものの失くしてしまった釣り針を探して「海神の宮」に行き、娘の豊玉姫を娶って海の支配権も獲得した。
地上に戻った山幸彦は、海神に与えられた魔法の玉を使って、海幸彦(隼人)を服属させた。
山幸彦と豊玉姫の子、ウガヤフキアエズも海神の娘、玉依姫と結婚し、皇室と海の結びつきが強化された。そして二人から、地上と海の完全なる支配権を身に着けた「神日本磐余彦(かむやまといわれひこ=神武天皇)」が誕生した。
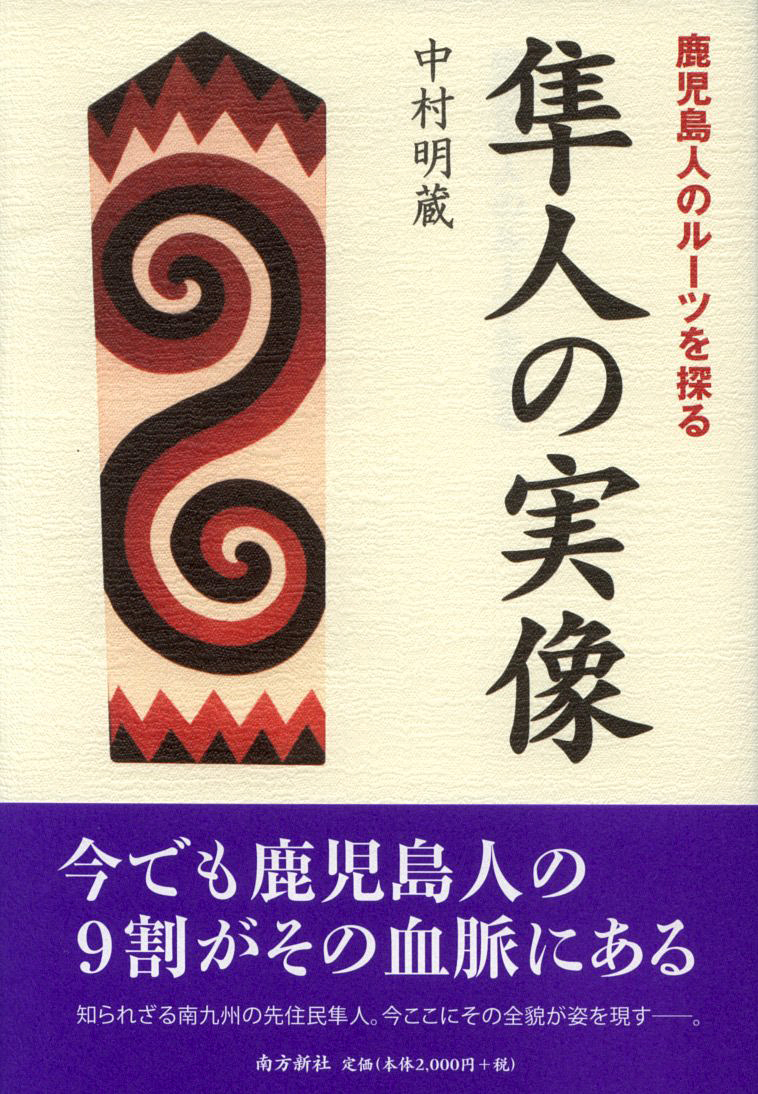
———といった話が、日本書紀の本文に書かれた「日向神話」の概要で、なにゆえに天皇が日本の領土領海と国民を支配していいのかを、説明する神話となっている。
だが、地元の鹿児島在住の研究者、中村明蔵さんによれば、日向神話を構成するパーツには皇室由来のものはなく、全てがもともとは隼人が語り継いできた神話だったものを、ヤマトが奪って自分たちの神話のラストに配置したのだという。
この神話には隼人の生活を反映した部分が多く描かれており、原話は隼人が伝えてきたものと見られる。
それを、天皇の祖(山幸彦)と隼人の祖 (海幸彦)の話に置き換え、山幸彦が海幸彦を服従させるという、巧みな構成に変えて政治的に造作したものであろう。
「釣り針を失くす話」の部分だけを取り出すと、類話は太平洋沿岸に広く分布する話でもある。
(『隼人の実像』中村明蔵/2014年)
釣り針を失くす神話自体は、ミクロネシアのパラオやインドネシアのケイ諸島、スラウェン島の「ミナハッサ」と著しく類似していて、そこらに祖型があるらしい。
(『日本神話の源流』吉田敦彦/1975年)
また、カシツヒメの別名を「神吾田津姫」ともいうが、「吾田」は薩摩国阿多郡を指していて、中村さんは「(南さつま市の)金峰山を祭る巫女」がカシツヒメの実体だろうと書かれている。
つまりはヒメは隼人の「山の女神」ということで、神代紀では「海幸彦」を演じる隼人は一方では「山幸彦」でもあって、689年に初めて朝廷に届けられた隼人の貢物は「牛皮6枚、鹿皮50枚」という山の幸だった記録が残っている。
また、隼人の土地では仏教弘布(692年)以降も、ずっと肉食(主にイノシシ)が当たり前に続けられていたそうで、漁労民にして狩猟民(少し農耕民)だった隼人の姿が見えてくる。

火中出産と海神の宮
カシツヒメの別名で、史上に名高い絶世の美女として有名な「コノハナノサクヤヒメ(木花之開耶姫)」は、醜い姉の「イワナガヒメ(磐長姫)」の対比として登場し、人間の寿命が短い理由を説明するときに使われる名前だそうだが、その「バナナ型神話(はかないバナナをとるか永遠の石をとるか)」も、インドネシアからニューギニアにかけて広く分布する神話なのだという。
またカシツヒメの「火中出産」も、インドネシアからインドシナ半島でみられる「産婦焼き」の習慣がルーツだと考えられているようだ(産婦の近くで火を燃やす行為で、産婦を燃やすわけではない)。
無事に出産できれば、身の潔白は証明できるというのだ。燃えさかる火の中で産声をあげたのが、ウミサチ・ヤマサチで知られる火照命、火遠理命ら兄弟である。
「産屋で火をたくのは奄美地方にあった海洋民の習俗で、妊婦を温めるとともに悪霊を祓う意味もあります」
宮崎県教育庁文化財課の本郷泰道専門主幹はそう話す。サクヤビメの奇抜な行為には、阿多が受け入れた南方文化の色が濃いという指摘である。
(『神話のなかのヒメたち』産経新聞出版/2018年)
なお、神話学者の松前健さんによれば、山幸彦が海神の宮殿でもらったシオミツ・シオヒルの玉の伝承は、博多湾の海人族「安曇氏」がもつ神話が、ヤマトに取り込まれたものだという。
『太平記』などが伝える神功皇后伝説では、シオミツ・シオヒルの玉は「阿曇磯良」が皇后に献上したとされているし、神代紀の一書で海神が山幸彦を接待する時の様子は、古代の安曇族が宮中で天皇に奉仕した職掌が、反映されているのだという。
(『日本神話の謎がよくわかる本』松前健/2007年)

日向神話はいつ取り込まれたか
平安時代の隼人は、朝廷の儀式には肩巾(ひれ)など呪力をもった服装で参列して、犬の鳴き声(吠声・狗吠)をあげて邪気を払う役目についていたという。また、山幸彦に降伏した海幸彦が演じた「溺死」のダンスは、その後、大嘗祭の御前で「隼人舞」として繰り返された———んだそうだが、要は「呪術」だ。
中村さんによれば、律令国家が目指す中央集権の確立のために、隼人に対しては武力行使とあわせて「信仰的・精神的面からの作戦」もとられたのだという。それが神話の取り込みと、天皇系譜への部分的な同化だった。

日本書紀には、天武天皇11年(682)7月、歴史上はじめて隼人が朝廷に参上して貢物を献じた、という記録がある。
もしも『古事記』がその序文どおりに成立したというなら、天武天皇が稗田阿礼に口伝できたのはこの頃だけなので、日向神話は天武朝末期にヤマトに取り込まれたことになる。
中村さんによれば、ヤマトは隼人の神話を取り込んで「ワタツミの呪能の力を骨抜き」にするという呪術を行うことで、信仰面や精神面から隼人を征服しようとしたのだという。
天皇家の祖となるヒコホホデミ(山幸彦)が釣り針を求めてワタツミの世界に行く。
そこまでは、阿多地域神話の原話の一次的改変であるが、つぎにワタツミの娘(トヨタマヒメ)との結婚となり(二次的改変)、さらにワタツミのもつ潮の干満を自由にできる二つの珠(呪力)を入手して帰還する(三次的改変)。これによって天皇家の祖はワタツミの呪能の力を骨抜きにしたのであった。結果、阿多隼人の祖であるホデリ(海幸彦)は天皇家に降伏したのである。
(『隼人の実像』)

日向三代と隼人の火の神
「日向三代」の御陵(お墓)は、宮内庁によってニニギが薩摩川内市、山幸彦が霧島市、ウガヤフキアエズが鹿屋市に治定されているが、平安中期の辞書『和名類聚抄』には、ニニギの「可愛山陵」は薩摩国頴娃郡、山幸彦の「高尾山上陵」は薩摩国肝属郡(もしくは阿多郡)にあると書いてある。
Googleマップだとこうなる。

宮内庁がいうよりずっと南で、ヤマトから見れば隼人世界の最奥部といっていい。
なので神話学者の松前健さんは、これらの墓の主は「まさしく隼人族の出身」で、日向神話とは元々は隼人が伝えた英雄伝説だったのだろうと言われる。
実際、火中出産の三皇子だが、新しく加わった神話のせいか、日本書紀の一書(参考文)は未整理状態のままで、人数が二人だったり四人だったりとまるで定まらない。
それで、毎度ビシッと整理整頓されてる『古事記』の方をみてみれば、最初に「火照命」(ホデリ=隼人の祖)、次に「火須勢理命」(ホスセリ=詳細不明)、最後に「火遠理命」(ホヲリ)で「亦の名は天津日高日子穂穂手見命(ヒコホホデミ)」とある。
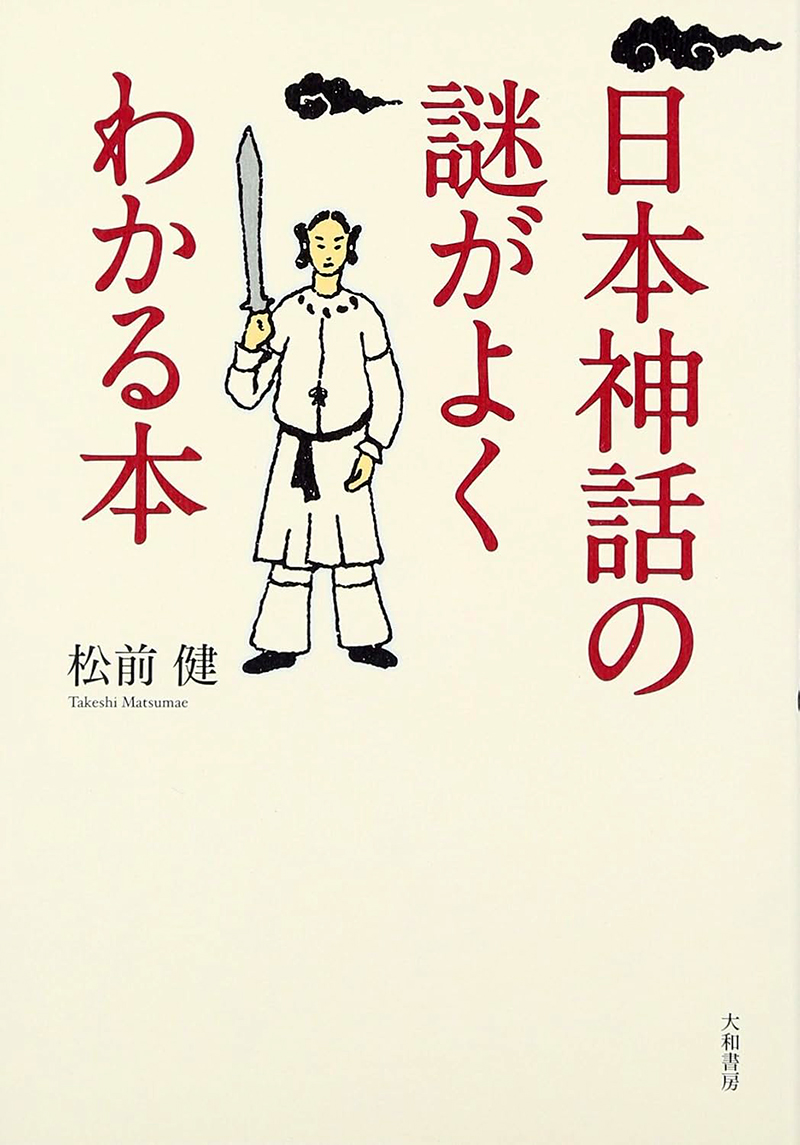
古事記の分かりやすいところは、三人の「火の神」を出したあと、「火」とは全くカンケーない「穂」の神がくっつけられている状況が、クリアに可視化されていることだ。日本書紀はヒコホホデミの「ホ」を「火」に当てて関連付けているが、これはチト無理やりにも思える。
というのも松前さんによれば、ニニギとは「稲穂が赤らみ、にぎにぎしく稔るさまを表す神名」で、その父「天忍穂耳尊」は名前にモロに「穂」がある。つまり、オシホミミーニニギーヒコホホデミは三代とも「稲作」に関係した名前を持つわけで「火」とは何もカンケーがない。
なのでここにでてくる「火の神」は、本来は隼人が祀ってきた神であろうと、松前さんはおっしゃるわけ。

二人のヒコホホデミ
ところで日本書紀は、「神日本磐余彦天皇(神武天皇)」の「諱」を、「彦火々出見」だと書いている(古事記にその諱は出てこない)。日本書紀を信じれば、祖父と孫が同じ呼ばれ方をしたことになる。
こういう場合、歴史学や神話学では「同一人物」を疑うわけで、歴史学者の和田萃さんは「憶測」だと断りながら、「かつてニニギ命とコノハナサクヤヒメの間に神武(イワレヒコ)が生まれたという系譜があった可能性もある」と話されている。
(『海人たちの世界』2008年)
つまり「日向三代」は実際には一代で、天孫ニニギから即、神武天皇につながったということになるわけだが、日向神話の神々を元は隼人の神だとして除外すれば、ストーリー的には「天孫降臨」と「神武東征」の間隔が短くなって話がスムーズだし、東征中の神武天皇がニギハヤヒらに「皇孫」と呼ばれることへの軽い違和感も消えていく。
それに、天孫ニニギの子が神武天皇だという説のほうが、なぜ神武天皇が宮崎出身なのかという疑問について、ぼんやりヒントが見えてくる気もする。

長浜浩明さんの計算によれば、神武天皇の生誕はBC96年頃のこと。
仮に、もともとは神武天皇の家族はもっと都会の(失礼!)北部九州に住んでいたとして、しかし父親(ニニギ)の代に何かとんでもない大事件が起きてしまい、その結果、一家で宮崎まで都落ちせざるを得なかったのだとしたら・・・。
そして宮崎で生まれ育った神武天皇は、できればもっと安全な場所に引っ越したいと思い続けていたのだとしたら・・・。
———BC108年、漢の武帝による朝鮮半島への軍事侵攻が開始され、今の平壌に「楽浪郡」が設置された。そのことへの恐怖は、戦争における中国人の残虐性を知るものであれば、心底ビビリまくるような話だったことだろう。
あの日、北部九州のニニギ一家は、海の向こうのことだと思っていた「軍靴の響き」を聞いてしまったのだった。
神武天皇(6)へつづく



