神武天皇はなぜ熊野へ行ったのか
日本書紀によれば、河内の日下(孔舎衛坂)でナガスネヒコ軍と戦った皇軍は、流れ矢が長兄「イツセ(五瀬命)」の脇に当たるアクシデントもあって、苦戦した。
神武天皇は「日の神の子孫であるのに、日に向かって賊を討ったことは天の道にそむいて」いると判断して撤退し、船団を南下させた。しかし残念ながら、紀伊国の竈山に着いたとき、長兄イツセは薨去してしまった。
神武東征、第2の謎?はこの後だ。
紀伊の名草邑で女酋の「名草戸畔」を討った神武天皇は、眼の前に船団を運用しやすい「紀ノ川」があるのにも関わらず、なぜか船団を南下させると、メッチャ遠回りで危険極まりない海域、熊野灘に進んだのだった。

迂回の目的はナガスネヒコの本拠地、生駒市の「鳥見」を東から(=奈良駅の方から)攻めることなので、紀ノ川をさかのぼって五條市で上陸し、葛城市を北上すれば早いと思われるが、なぜ神武天皇は危険な熊野灘を目指したのか。
現に熊野灘では、次兄の「イナイ(稲飯命)」、三兄の「ミケイリノ(三毛入野命)」が相次いで溺死してしまい、神武天皇の肉親は息子の「タギシミミ(手研耳命)」だけになってしまった。
日本書紀にはイナイとミケイリノの今際の言葉が載っているが、「日向神話」の意味を全否定するような悲痛な叫びで、正史がこれを採録した意図がよくわからない。
そのとき、稲飯命はなげかれて、「ああ、何としたことだ。わが祖先は天神、母は海神であるというのに、どうして私を陸で苦しめ、また海で苦しめるのだろうか」と仰せられ、言いおわると、そのまま剣を抜いて海に入って鋤持神(さいもちのかみ)となられた。
三毛入野命もまた恨んで、「母と姨(おば)とは、二はしらとも海神である。それなのにどうして、波をたてて私をおぼれさせるのか」と仰せられて、浪の穂をふんで常世郷(とこよのくに)に行ってしまわれた。
(『日本書紀(上)』中公文庫)
まぁ強いて理由をひねり出すなら、(神ではない)人間の皇統は神武天皇に一本化されていることを、広く周知させることが目的だった、とか?
ちなみに『古事記』には二人の兄の溺死はでてこない。「稲氷命」と「御毛沼命」は海で死んでいる点は同じだが、それは東征以前のことで、古事記の神武天皇は「五瀬命」と二人で東征に出発したと書いてある。

熊野の高倉下と霊剣「ふつのみたま」
神武天皇が熊野を目指した理由を、実際に起ったことから逆算して考えれば、3つの可能性があるか。
1)イナイとミケイリノを溺死させるため(これは陰謀論)
2)熊野の女酋「丹敷戸畔」を殺すため(これは結果論)
3)熊野の高倉下から「ふつのみたま」を受け取るため(これか!)
「ふつのみたま(韴霊)」の件は、熊野の神に祟られて苦境に陥った天皇を見かねて、アマテラスがタケミカヅチに命じて「高倉下(たかくらじ)」に下賜した———と日本書紀は書くが、これ全て高倉下が睡眠中に見た「夢」のはなし。
事実はその霊剣が、高倉下の「庫(くら)」に置いてあったことに尽きるだろう。
高倉下が何者かは日本書紀には書いてない。書いてあるのは、平安初期に物部氏の末裔が撰録したという史書『先代旧事本紀』で、それによれば物部氏の祖・ニギハヤヒが天上界で授かった子「天香語山(あまのかごやま)命」の、「亦の名」が高倉下だという。
つまり物部氏の伝承では、高倉下はニギハヤヒの子だとされているわけ。

実はニギハヤヒにはもうひとり男子がいて、地上に降臨してからナガスネヒコの妹との間に授かった「ウマシマジ(宇摩志麻治命)」。
『先代旧事本紀』によれば、神武天皇は高倉下から献上された「ふつのみたま」をこのウマシマジに与えたとあって、またの名を「布都主神魂(ふつぬしのかむたま)の刀」といったのだという(「天孫本紀」)。
神話学者の松前健さんによれば、軍事氏族の物部氏が「国土鎮定の呪宝」として各地に奉じていった霊剣が「ふつのみたま」で、それを人格化させたのが”出雲の国譲り神話”に登場する武神「フツヌシ(経津主神)」だという。
(『日本神話の謎がよくわかる本』)
その物部氏の氏神、フツヌシが再び剣の姿に戻って、ニギハヤヒの二人の子の間を、神武天皇の手を通じて移動した———というのが『先代旧事本紀』の記述から見えてくる話になると思う。

熊野三山と物部氏
ところで熊野といえば「本宮」「速玉(新宮)」「那智」の熊野三山、というのが古代史好きの反応だろうが、こちら物部氏との縁が非常に深い神社として知られている。
熊野那智大社の宮司を勤められた篠原四郎さんの『熊野大社』(学生社/1969年)によると、熊野では長らく高倉下の子孫が祭政を担ってきたが、成務天皇(長浜浩明さんの計算で在位320−350年)の御代に「熊野国造」としてニギハヤヒ5世孫の「大阿刀足尼(おおあとすくね)」が任命されると、高倉下の子孫は新宮(速玉)の祭事に専念することになったのだという。
それが「熊野三党(新宮三党)」といわれる、宇井・鈴木・榎本の三氏。

ただ三氏は分かれる前は「穂積氏」といって、穂積氏といえば物部氏の最有力支族。河内日下の「石切劔箭神社」の神職も、穂積氏の末裔「木積氏」なんだとか。
んで残る那智は、元々お寺としてスタートしていて、最も古い社家はやはり高倉下の子孫を称する「潮崎氏」・・・といったかんじで、熊野三山の成立には、熊野土着の高倉下の末裔か、(世代数は合わないが)ニギハヤヒ五世孫の末裔が入り混じりつつ関わっていて、熊野は”物部宗教王国”の様相を呈していたようだ。
すると篠原宮司の『熊野大社』には興味深い話が載っていて、熊野本宮大社の「八咫烏神事」では「太陽神」を祀っていたのだという。
記紀や天孫本紀の記述によると、神武東征以前にはすでに天津神の御子が大和国に天降っていたということから、熊野の地に住み着いた天孫系神別諸氏の日神信仰によって創立したのがこの本宮であったと考えられる。
それは熊野の大神の神遣が太陽の化身「八咫烏」であることも本宮祭神の始元が日神であったことを物語っていると思われる。
本宮大社に伝わる「八咫烏神事」は太陽の蘇りを顕す祭りで、年が改まったのに当たり太陽の光と共に素戔嗚命の広大慈悲な御神徳が再び蘇って戴くという、まさに熊野信仰がそのまま凝縮され、形となったような御祭りである。
太陽の化身と素戔嗚命の御神徳が一年に一度蘇る祭り、それが「八咫烏神事」である。当社の大神の御遣い「八咫烏」は太陽の化身である。
(「本宮の神事」)
篠原さんは宮司というお立場上、公式の主祭神であるスサノオの名を出されるが、「天孫系神別諸氏」の日神はアマテラスなので、スサノオと並べて祀ることはないと思われる。
そうすると思い浮かぶのが、河内の物部氏が日下の地で礼拝したという「饒速日山」の件。
河内の物部氏にとってはニギハヤヒこそが太陽神(日神)だったわけで、熊野の物部氏にとっても、太陽神といえばニギハヤヒだった可能性はあるんじゃないだろうか。
余談になるが、日本書紀ではアマテラスが皇軍の先導者として派遣した「頭八咫烏(やたがらす)」は、最初は鳥の姿で現れて空を飛んだとされているが、神武天皇の即位の際には人間として論功行賞が行われていて、その子孫は「葛野主殿県主部」なのだという。
「葛野県主」は山城国に移住した「鴨氏」の後裔らしいので、この話は東征当時、大和の葛城に住んでいた鴨氏が、何らかの理由で熊野まで神武天皇の道案内に駆けつけたことを意味しているのかも知れない。

「ふつのみたま」の献上と高倉下の降伏
なぜ神武天皇は熊野に迂回したのか———に話を戻す。
確かに紀ノ川をさかのぼった場合は、行った先で現地に地の利のあるナガスネヒコに待ち伏せされる恐れはある。それで隠密行動がとれる熊野川〜十津川ルートに迂回した可能性はあるが、それにしても失うものが多すぎた。
それでも神武天皇には、死を賭してでも熊野を目指す理由があったのだとしたら、日本書紀を読む限り、それは高倉下と「ふつのみたま」にあったとしか考えにくい(他には大したトピックもないので)。
繰り返しになるが、高倉下はニギハヤヒが天上界で儲けた子で、「ふつのみたま」は物部氏の霊剣だ。日本書紀は熊野の神が現れて〜〜と装飾するが、そこで起こったことは、高倉下が物部の霊剣を天皇に献上した、の一点に尽きると思う。
んで歴史学者の岡田精司さんによれば、そういう行為は部族の降伏を意味するのだという。
このように古代では武力で平定するのと、呪禱で祈り倒そうという行為が一体であったとなれば、征服したら必ずそこの豪族の持っている神宝を取り上げることが重要になります。
これが記紀の伝承の中にも出雲の国造の神宝を持って来たり、アメノヒボコの持っている神宝を取り上げるとかいう形であらわれています。
(中略)彼らの持っている守護神の象徴になるような大事なもの、そこに国魂がひそんでいるものと考えていた。それで降伏した豪族には必ず神宝を差し出させるのです。
(『神社の古代史』岡田精司/1985年)
だいぶ後の時代になるが、引用にあるように「出雲」も「アメノヒボコ」もヤマトに神宝を取り上げられて、帰順、降伏している。同じことが熊野でも起こった可能性はないんだろうか。
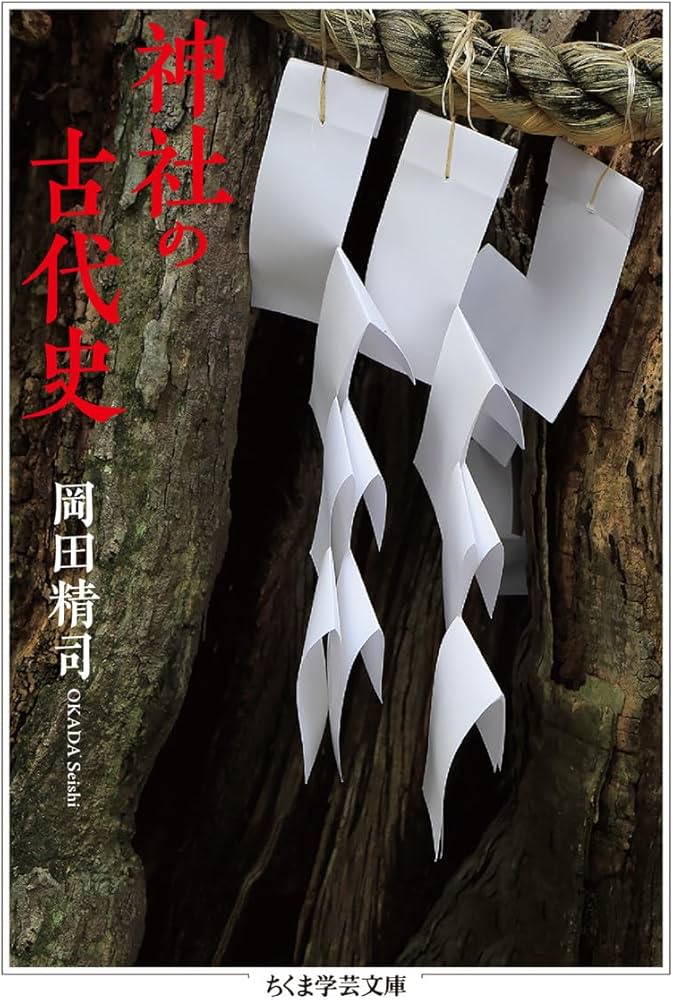
高倉下が、ニギハヤヒの「子」である点も気になる。
このあとニギハヤヒは、神武天皇に”大和の国譲り”をすることになるが、それ以前の”国譲り”といえば、言うまでもなく出雲のオオクニヌシ(大己貴神)。あのときオオクニヌシは、その判断を「息子」とされるコトシロヌシに委ね、先に「子」が降伏したことで、親の降伏も決定した(未来から潰した?)。
ニギハヤヒも「子」の高倉下が天皇に神宝を献上して降伏したとき、物部氏に課せられた、抗いがたい定めを思い出したのかも知れない。
ちなみに神代紀の本文で出雲をくだしたのはフツヌシだが、現実世界で出雲をくだしたのも、矢田部造の祖にあたる「武諸隅(たけもろすみ)」という物部氏だ(崇神天皇60年)。

熊野の考古学
新宮市には、徐福が探し求めた「蓬莱山」だといわれる山があって、その麓に鎮座している「阿須賀神社」の境内からは、弥生時代の竪穴住居跡や、祭祀用の手捏小型土器や滑石製臼玉などが出土している。
また、神武天皇が登った「天磐盾」と目される「ゴトビキ岩」の周りからは、銅鐸の破片が大小22個出土していて、熊野にフツーに弥生人の営みがあったことが確認されている。

ところが不思議なことに、新宮市・熊野市・尾鷲市の界隈からは、古墳がひとつも見つかっていないのだという。
考古学者の穂積裕昌さんはこの点について、同じように古墳が造営されなかった大神神社や石上神宮の近辺なら「穢れ忌避意識」で説明できるが、神話的には「死者が赴く国」のはずの熊野にそれは当てはまらない、と疑問を呈されている。
(『海人たちの世界』2008年)
そうなるとぼくなどは、古墳時代までの熊野は「死者の国」なんかじゃなくて、死穢を遠ざけるべき「聖地」として考えられていたんじゃないかと思ってしまうんだが、よっぽど偉大な神様が祀られていたんじゃないかなぁ、オオクニヌシ級の。
神武天皇(9)につづく




