倭にのぼらない大国主神
古事記と日本書紀の大きな違いに、いわゆる「出雲神話」の扱いがある。
誰でも知ってる「稲羽の白ウサギ」「八十神の迫害」「根の堅州国」「越の沼河比売との恋」といったオオクニヌシの大冒険は古事記にしかなく、日本書紀は無視している。
だがこの点については、日本書紀は日本の歴史ではなく「天皇の歴史」を書いた本だといわれれば、言及がなくても不思議ではない話。
そこではなく、記紀の両方にのる説話にこそ、両者の決定的な違いがあることを教えてくれたのが、上代文学を専門にされる松本直樹さんの『神話で読みとく古代日本』(2016年)という本だ。
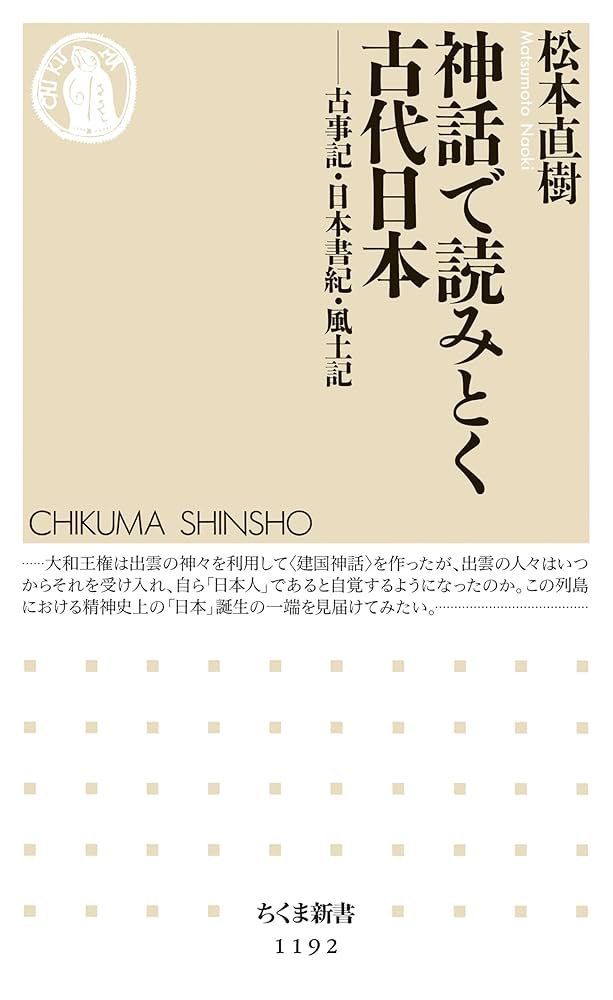
松本さんによれば、古事記は「用語・用字のレベルに至るまで相当に綿密な計算がなされ、それが全体の主題、文脈を支えている」「完成度の高い作品」だという。
ところがそんな古事記に「単なる不手際として片付けることができない」「かなり大きな傷」があって、そのひとつがオオクニヌシの「国作り条」。
あるとき、相棒のスクナヒコナに去られ、途方に暮れるオオクニヌシの前に「海上を照らして」近寄ってきた神が、「わたしの御魂を祭ったならば」協力して国作りを完成させることができる、といってきた。
そこで大国主神が、「それでは御魂をお祭り申しあげるには、どのように致したらよいのですか」と申されると、「わたしの御魂を、大和の青々ととり囲んでいる山々の、その東の山の上に斎み清めて祭りなさい」と答えて仰せられた。
(『古事記(上)』講談社学術文庫)
これが御諸山の上に鎮座しておられる神である。
古事記の「国作り条」の流れからすれば、オオクニヌシがその神を祭り、国作りを完成さたことは間違いなさそうだが、古事記には「その神を祀ったという明確な記述がない」のはなぜか。これが古事記の「傷」だ。
なぜなら日本書紀の同じ説話には、オオクニヌシが自らその神を三諸山に祀ったことがはっきり明記してあるからだ。
大己貴神は、
(『日本書紀(上)』中公文庫)
「たしかにそのとおりだ。たしかにおまえは私の幸魂奇魂である。いまどこに住みたいか」
と尋ねられた。その神は答えて、
「私は日本国の三諸山に住みたいと思っている」
と仰せられた。そこで大己貴神は神宮を三諸に造営して、住まわせられた。
つまり日本書紀のオオクニヌシは、出雲から倭(やまと)に移動して自由に行動しているが、古事記のオオクニヌシが倭に踏み入っているかどうかは、不明瞭だということ。
それが明瞭になっているのが、古事記でオオクニヌシが「高志(越)」のヌナカワ姫に求婚したあとの話。
正妻であるスサノオの娘・スセリ姫のジェラシーにビビったオオクニヌシは、「出雲より倭国に上りまさむとして」荷物をまとめるが、いよいよ旅立ちというときになって、スセリ姫の愛の歌に心を打たれ、倭行きを取りやめて「今に至るまで鎮まります」という説話がある。
スセリビメの嫉妬によって、オホクニヌシは倭には「上る」ことができなかった。スサノヲの子孫であるオホクニヌシに倭だけは支配させないことが、この段の趣旨であったと思うのである。
(『神話で読みとく古代日本』松本直樹)
こうして、確かにオホクニヌシだが、完全ではないオホクニヌシが誕生したということである。
どうやら古事記には、出雲と倭(やまと)の間に見えない「境界」のようなものがあって、大国主神はその線を跨がないが、日本書紀の大己貴神には「境界」はなく、出雲と倭を自由に行き来してしまうようだ。
そしてその行動パターンは、オオクニヌシの周囲の神々にとっても、同様だった。

天と地のアジスキタカヒコネ
古事記によれば、大国主神と宗像三女神のタキリ姫との間に生まれた子に「阿遅鉏高日子根神」がいる。
「天孫降臨」に先立って、葦原中国の平定に2番目に派遣された神が、アメノワカヒコ(天若日子)だったが、大国主神の娘、シタテルヒメを娶って葦原中国に住みつくと、8年ものあいだ復命してこなかった。
いろいろあって結局、アメノワカヒコはタカミムスビの放った「返し矢」に射られて死亡、その喪屋が地上につくられて、そこに親友のアジスキタカヒコネが弔問にやってきた。
このとき、アメノワカヒコの家族は天から降ってきているが、アジスキタカヒコネは地上を歩いて移動してきただけだ。
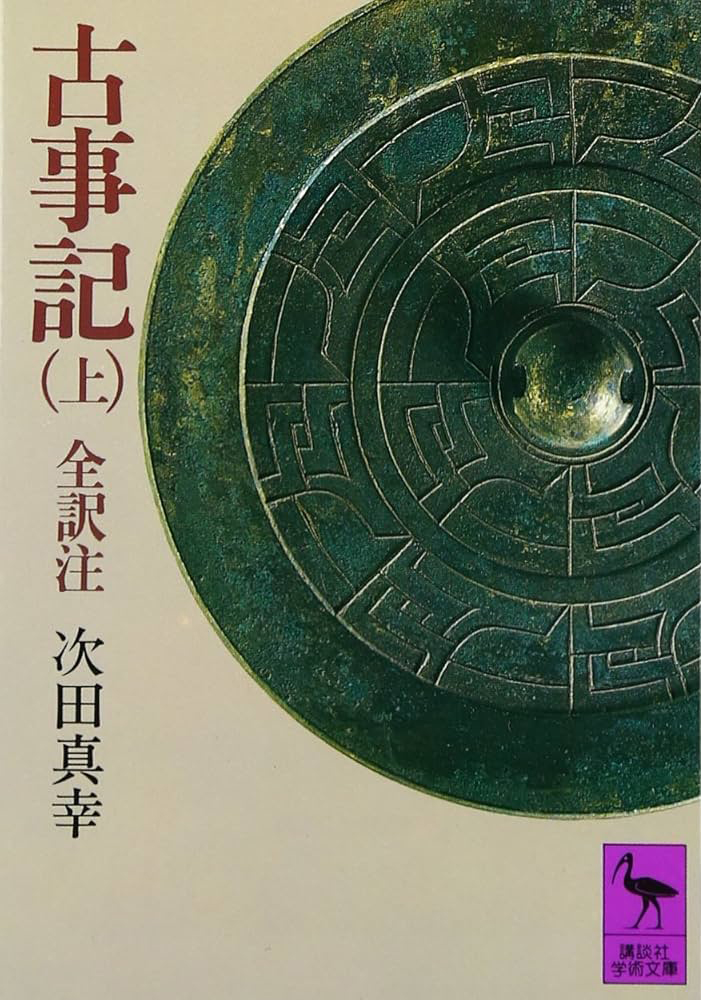
一方、日本書紀では母親不明で登場した「味耜高彦根神」は、こちらの世界でも同じく「反し矢」で射殺された親友のアメワカヒコ(天稚彦)の弔問に出かけている。ただし喪屋の場所が違っていた。日本書紀ではアメワカヒコの亡骸は「天」に運ばれて、天の喪屋で殯(もがり)が行われたのだ。
つまり日本書紀のアジスキタカヒコネは、葦原中国から(古事記がいうところの)高天原に移動しているというわけだ。理解を深めるべく、ここでもう一度、オオクニヌシと「倭」について、松本さんの解説を引用。
実はこの「倭」こそ、地上に復元された「高天原」の聖地であり、後に神武が到達し、史上初めて「天の下」を統治する舞台なのである。
(『神話で読みとく古代日本』松本直樹)
だから「天の下」の頂点である「天」=「倭」の支配権だけは、オホクニヌシに握らせるわけにいかなかった。そもそもオホクニヌシは、「高天原」を追放されたスサノヲの子孫なのであるから。
国作り条において、倭の青垣山での祭祀が明記されていないのは、オホクニヌシの力を「倭」にだけは及ばせないためであろう。
しかし日本書紀には、葦原中国=出雲と、高天原=倭のあいだに「境界」がないので、オオクニヌシの子、アジスキタカヒコネは天と地を自由に行き来している。

幽冥界と皇室外戚のコトシロヌシ
記紀の両方でオオクニヌシの子とされるのが、父の代わりに「国譲り」を決断したコトシロヌシ(事代主神)だ。
この神は、高天原の使者に国土を譲渡する意思を告げると、日本書紀では「退去」、古事記では「隠れ」たとあるが、要はオオクニヌシ同様に「幽冥界」に退去、隠匿したとみるのが定説のようだ。
んで古事記のコトシロヌシの出番は出雲で終わりになるが、日本書紀のコトシロヌシは、今度は大和に現れた。娘のヒメタタライスズ姫(媛蹈鞴五十鈴媛)の美貌を聞きつけた即位前の神武天皇に求められ、その岳父となっている。
つまり第二代綏靖天皇、第三代安寧天皇には母方のおじいちゃん、第四代懿徳天皇もコトシロヌシの四世孫(玄孫)ということで、皇室の「外戚」第一号だ。
日本書紀をアタマから順に読み進めてきたら、出雲で死んだコトシロヌシは「境界」を超えて大和に現れ、皇室の母方の祖神になったように読めるはず。
———もちろん、実際の「事代主」は人間で、大和葛城地方に土着していた豪族「鴨氏」の総帥だったんだろう。それが東征してきた神武天皇と婚姻政策で結ばれて、皇室を支える大黒柱になり、のちに神格化されたんだろう。
事代主は律令時代には宮廷で「託宣」の神として祀られているので、その特殊能力を買われ、「国譲り」を託宣する神として神話に引っ張り出された———と、神話学者の松前健氏は書かれている(『日本神話の謎がよくわかる本』)。
もちろん、出雲のオオクニヌシとは縁もゆかりもない存在だ。
スクナヒコナは誰の子か
オオクニヌシの国作りの相棒、スクナヒコナ(少彦名)は、日本書紀では「皇祖」タカミムスビの子として登場する。
つまり、天石窟からアマテラスを引き出す策を練った「知恵の神」オモイカネや、天孫ニニギの母・栲幡千千姫とはキョウダイだということだ。当然、うまれは「高天原」だろう。
一方、古事記のスクナヒコナ(少名毘古那)はカミムスビ(神産巣日神)の子。
カミムスビは、日本書紀だと名前が一度出てくるだけの実態のない神だが、古事記だとスサノオを殺したオオゲツ姫から生まれた食物を回収したり、八十神に殺されたオオクニヌシを蘇生させたりと、どうやら出雲(葦原中国)の国作りを統括する神らしいという。
ちなみに『出雲国風土記』からは、スサノオより古い時代から島根半島一帯にカミムスビの信仰圏が広がっていたことが読み取れる(スサノオの信仰圏は出雲南部の丘陵や山地)。
カミムスビは、もともとは出雲の古い神だったが、国作りを監督する神として、古事記の神話に取り込まれた———というようなことが、松本さんの本に書いてある。

ところで、一般的には出雲を大きくフィーチャーするのは古事記の方で、日本書紀は出雲への関心が薄いとされるが、スクナヒコナについては、それは当てはまらないようだ。
カミムスビに、オオクニヌシと「兄弟(あにおと)」となって国作りをしなさい、といわれたスクナヒコナの実際の行動を、古事記は「二柱の神が共々に協力して、この国を作り固められた」としか書いておらず、何ともあっさりしたものだ。
一方、日本書紀の記述は詳しい。
さて、大己貴命と少彦名命とは力をあわせ、心を一つにして天下を経営された。またこの世の青人草と家畜のためには療病の方法を定められ、鳥獣や昆虫の災異を除くために、まじないはらう方法を定められた。だから百姓(おおみたから)は今に至るまでみなこの神の恩をうけているのである。
(『日本書紀(上)』中公文庫)
この記述からスクナヒコナを医療の神とする信仰がうまれたそうだが、ポイントは「この神の恩」を受けているのが、出雲の人間に限らないことだ。
古事記のスクナヒコナの「国」作りは、例の曖昧な表現によって、出雲に限定された話にも読めるが、日本書紀のスクナヒコナの影響は葦原中国の全域に及んでいる。
ぼくはここにも、「境界」のある古事記、「境界」のない日本書紀という違いを感じざるをえない。

スサノオの「母」とは誰のこと?
それにしても、やっぱりプロの学者は鋭いよなーと感じたのが、松本さんが本のなかで指摘されている古事記のスサノオの異常なセリフの件。
セリフは二つあって、一つは泣きわめくスサノオに、父のイザナキがその理由を聞いたときのスサノオで「私は亡き母のいる根の堅洲国に参りたいと泣いているのです」。
もう一つが、クシナダ姫に求婚し、名前を問われたときのスサノオで「私は天照大御神のいろせ(同母弟)である」。
でもスサノオに母親がいるのは日本書紀の本文(正伝)の場合であって、古事記のスサノオは黄泉の国から帰還したイザナギが、阿波岐原で鼻を洗ったときに成り出でた神———だったはず。
古事記のスサノオに母はいないし、同母姉もいないというわけ。
・・・むー、ぼくはあまり古事記は読まないので、実を言うとこの件、まったく気づいていませんでした。お恥ずかしい・・・orz。
んで、そうなると、スサノオにイザナミという母がいる方が古いオリジナルのストーリーで、古事記の「黄泉津大神」なんておどろおどろしいのは、後から何らかの理由で挿入・改変された新しいものという気がしてくる。うっかりか故意にかは不明だが、残されてしまった上記のスサノオのセリフがその根拠になりそうだ。
そしてそうなると、古事記でイザナミのお墓が出雲と伯耆の境の寂しい「比婆山」にあるなんてのも、イザナミを出雲の側に寄せたい古事記の意図(悪意?)を、感じてしまう。
日本書紀のイザナミの墓所は、明るい太陽に照らされる熊野の有馬村(花の窟)で、そこで人々は花を飾り、にぎやかに歌い舞い踊ってイザナミの魂を鎮めるのだという。
古事記と日本書紀(6)につづく




