 邪馬台国
邪馬台国 (1)邪馬台国畿内説の「萬二千餘里」は「記号的数値」か
「萬二千餘里」は「記号的数値」か邪馬台国の「謎」はつまるところ、その所在地の問題につきるだろう。昔から、魏志倭人伝の「方位」をとれば九州に、「距離」をとれば畿内(大和)に、で争われてきたそうだが、現代人よりは漢文が身近にあった新井白石や本居...
 邪馬台国
邪馬台国  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇 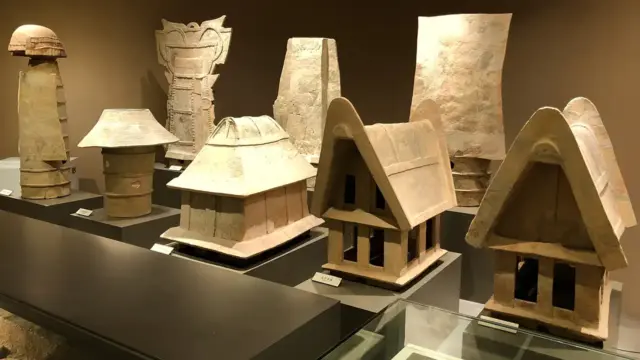 垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇  垂仁天皇
垂仁天皇  崇神天皇
崇神天皇  崇神天皇
崇神天皇  崇神天皇
崇神天皇