古事記成立の三段階説と藤原不比等
国文学者の神田秀夫氏によれば、音訓と字句の分布状況からは、古事記本文の成立過程には「古層(敏達朝前後)」「飛鳥層(舒明朝前後)」「白凰層(元明朝前後)」の三段階が想定できるのだという。
(『六国史以前』関根淳/2020年)
古事記はその序文によれば、元明天皇の勅命によって712年に成立したとされているが、その時代に元明天皇の近くにいて、修史にも口出しできる実力者といえば、右大臣「藤原不比等」以外には考えられない———というのが、宗教研究家の藤巻一保さんだ。
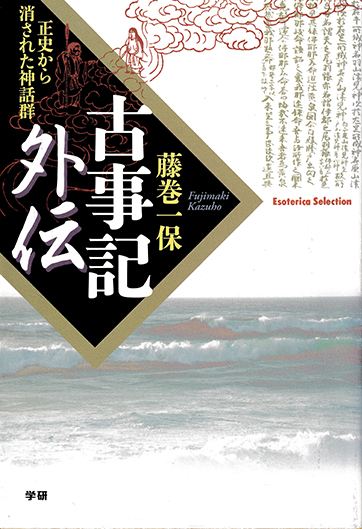
その著書『古事記外伝』(2011年)によれば、古事記とは藤原不比等(とその実家の中臣氏)が政治的意図をもって描いた「国家統治のグランドデザイン」なのだという。
その構想は、天皇を「形而下の世界(現実世界)と形而上の世界(神々の世界)の双方を統一する存在」であるとし、天皇による「祭政両面で遺漏のない支配の完成」を描くことにあった。
つまり古事記で天皇を持ち上げれば持ち上げるほど、その最側近の実務者として政治を取り仕切る藤原氏と、祭祀を執り行う中臣氏の価値も高まっていくという話だろう。
このとき天皇が支配する「形而上の世界(神々の世界)」を表すために対置されたのが、「生」をつかさどる太陽の国・伊勢と、「死」をつかさどる出雲・・・という構図なので、まずは古事記が描く「伊勢」から。

伊勢のサルタヒコとアメノウズメ
日本書紀の本文(正伝)には出てこないが、古事記が大々的に取り上げるのが「サルタヒコ(猿田毘古神)」だ。サルタヒコは天降り目前の天孫ニニギの前に現れて、道案内を買ってでた「国つ神」だが、古事記はこの神を「大神」と称えて呼んでいる。
藤巻さんによれば、古事記でサルタヒコ以外で「大神」の尊称がついている国津神は、三輪山に鎮座する祟り神の「オオモノヌシ(大物主)」と、葛城山で雄略天皇と接触した「ヒトコトヌシ(一言主)」の二神しかおらず、あの大国主神でさえ「大神」とは呼ばれない。
古事記は伊勢のサルタヒコを、最上級の呼称で呼ぶべき重要な神だと主張しているわけだが、日本書紀の本文(正伝)がスルーしているように、もちろん本当に持ち上げたいのは伊勢神宮のアマテラスだ。
「大神」の一人であるサルタヒコより上位に、アマテラスが存在していることを強調するために、サルタヒコは持ち上げられている。
というのも、皇大神宮(内宮)で最高位の神職「禰宜」を世襲したのは荒木田氏だが、禰宜を含む全職員と神宮の政務の一切を束ねて君臨したのが「祭主」という地位で、それを幕末まで世襲したのが「中臣氏」だったんだそうだ。
藤原/中臣氏には、何が何でも伊勢神宮を持ち上げる必要があったというわけ。

藤原不比等が世に出たのは持統天皇(在位690−697)の頃だが、当時の「伊勢大神」は天皇に納税の相談をもちかけてくる地方神で、まだ皇祖神アマテラスの像を結んではいなかったらしい。
『二所太神宮例文』なる神宮の職員関係の事例集によると、中臣氏が伊勢神宮の「祭主」におさまったのは鎌足の父「中臣御食子(みけこ)」からというが、中臣氏が宮廷祭祀の実権を握るには伊勢神宮の地位向上が手っ取り早いわけで、アマテラスの「皇祖神」化、伊勢の「聖地」化は必須。
伊勢土着の太陽神・サルタヒコの「大神」化もその一環だったと藤巻さんはお考えだ。

サルタヒコとのからみで有名な「アメノウズメ(天宇受賣命)」も、日本書紀の本文(正伝)には出てこない。古事記のアメノウズメは天孫ニニギに従って天下りしてきた「五伴緒(いつとものお)」の一神で、後裔氏族は宮中の鎮魂祭を担当した祭祀氏族の「猿女(さるめ)君」。
カバネに「君」がつくのは「君姓の氏族は、かつては大王家、またはそれに準ずる権威を持った家柄」(岡田精司)という説もあって(三輪君、上毛野君、宗像君など)、猿女君は中臣氏より古くからの祭祀氏族であった可能性もあるのだとか。
それはさておき、あの時代、祭祀の独占を狙う中臣氏にはライバルがいて、それが「五伴緒」の一神「フトダマ」を祖神とする「忌部(いみべ)氏」だ。
藤巻さんによれば、宮中祭祀における中臣氏と忌部氏の職掌(祝詞の奏上、祈禱、奉幣など)は丸かぶりで、中臣氏としては忌部氏は排除の対象だったらしい。
が、職掌の異なる猿女君は、むしろ仲間に取り込んで利用した方が有利に働くので、古事記が猿女君のアメノウズメを大きく取り上げる背景には、そんな政治的駆け引きがあった可能性があるという話だ。
『日本書紀』の本文が、司令神としてのアマテラスも、五伴緒も、サルタヒコも、アメノウズメも、いっさい出さずに天孫降臨を描いていること自体が、『古事記』の天孫降臨神話は、天皇家自身の神話とはさして深い関連をもたない、いうなれば中臣氏の「事情」にもとづく神話だということを、暗に示していると筆者は考えるのである。
(『古事記外伝』)
なお古事記では、降臨したニニギはアメノウズメにサルタヒコの「猿」の神名を継がせ、サルタヒコを国(伊勢)まで送らせている。サルタヒコを送ったアメノウズメは魚たちを集めて天皇への服属を誓わせるが、ナマコだけが無言だったので、その口を刀で裂いたという。
この二つの説話の真ん中に、ひらぶ貝に手を挟まれて溺れたというサルタヒコの死が挟まれているわけだが、藤巻さんによれば、サルタヒコを含めて複数存在していた伊勢の太陽神がアマテラスに統合されたので、不用になった太陽神たちを代表して、サルタヒコの殺害が行われたのだという。
話の前後の流れを考えれば、このときサルタヒコを殺したのは、アメノウズメってことになるんだろうか・・・。

黄泉比良坂のイザナミとスサノオ
古事記の世界においては、ヤマトの東に「生」をつかさどる「伊勢」が、その対極のヤマトの西に「死」をつかさどる出雲が、配置される。
イザナミの扱いがわかりやすい。日本書紀の本文(正伝)のイザナミは、火の神を産まないのでホトを焼かれて死ぬことはない。アマテラスはイザナミが出産した女児だ。
一方、古事記のイザナミはカグツチを産んで焼死してしまい、出雲と伯耆の境にある「比婆山」に葬られ、その後「黄泉津大神」になって夫イザナギに襲いかかった。イザナギは「千引きの岩」で「黄泉比良坂」を塞いで黄泉の国から脱出すると、ケガレを祓うミソギを行う。
そのとき洗った顔の左目から成り出でたのが、アマテラスだ。
藤巻さんによれば、古事記は「イザナミを穢れの代表として」位置づけていて「皇祖神アマテラスをイザナミと切り離し、イザナギ単独の子」にしているのも、そのためだという。
つまりは出雲が「死の国」であることを強調するために、イザナミをわざわざ出雲に葬ったりしているというわけだ(日本書紀の一書だとイザナミの墓所は熊野の海人の聖地「花の窟」)。

スサノオも記紀で違った描き方をされる。
日本書紀の本文では、八岐の大蛇を退治して、奇稲田姫と結婚して大己貴命を授かったスサノオは「根の国」にいったという。日本書紀の「根の国」には別にダークでネガティブなイメージはなく、ただ「遠い遠い」場所だといわれるだけ。
なのでちょー有名な民俗学者の柳田國男は、根の国を沖縄の「ニライカナイ」のような「常世」のことだと言っている。
一方、古事記のスサノオが住むのは「根の堅州国」で、ここも黄泉比良坂の向う側にある世界だ。当然、スサノオはイザナミも住む幽冥界の住人ということになる。

出雲大社の創建
んで、以上のような古事記の世界観やストーリー、キャラ設定に対応する神社、すなわちオオクニヌシの幽冥界の宮殿は「必ず出雲国内になければならない」という中央政府からの要請に応えて、出雲国造家が創建したのが「杵築大社(今の出雲大社)」だと藤巻さんはいわれる。
ざっとその経緯を引いておくと、7世紀に入ってようやく出雲国全域を支配下においた出雲国造家が、出雲国の「神郡」の郡司と神宮司を兼ねるようになったのは、大化から天武朝の期間のどこか(645〜686年)。
この時点では出雲国造家の本拠地は意宇郡(松江市)で、「櫛御気野命(クシミケヌ)」なる謎の神を祀る「熊野大社」が奉斎社だった。その後、出雲国造家が本拠地を意宇郡から出雲郡の「杵築」に移したのが、第24代国造の「出雲果安(はたやす)」のときで、708〜721年のどこか。
この果安のときに(716年)、記録上ははじめて『出雲国造神賀詞』が奏上されていることから、このときを「杵築大社(出雲大社)」完成の報告と見る識者も多いようだ。

藤巻さんは、奈良時代の出雲国造家は一部で「特権的な地位」を認められていたが、その理由が「古事記の構想に沿った」出雲国の統治と、杵築大社の祭祀にあったという。要は、古事記の世界観を裏付ける物証が、杵築大社だということだろう。
杵築大社は、服属(国譲り)の永遠のシンボルであり、出雲国造家は、アキツミカミの御代がつづくかぎり、そのシンボルを守る使命を課せられた特別な氏族なのである。そのことは出雲氏の当主交替の際の神事や、杵築大社の神事に、端的に表れている。
(『古事記外伝』)
そして杵築大社は「服属のシンボル」であると同時に、古事記が打ち出す「新秩序のシンボル」でもあったという。その意味は三点。
1)天皇による、「国譲り」後の葦原中国の一元支配。
2)ヤマト王権の神統譜にあわせた、国内の神々の再編。
3)地上の「高天原」である伊勢神宮と、地上の「根の堅州国」である出雲を東西に置き、その二つの世界を中心にいるヤマト王権が統治するという、幽冥界まで含めた一元支配。
要は、高天原〜根の堅州国という垂直軸も、伊勢〜出雲という水平軸も、全部ど真ん中のヤマトが支配するという構図を描き、その構図で表される新秩序を「実務面で取りしきる者」すなわち「藤原・中臣氏による祭政の掌握」こそが、古事記が本当に訴えたいこと、ということだ。
皇室の正史・日本書紀の編纂が国家事業として行われている、まさにその横で、古事記は別の意図をもつ人たちの手で、彼らの都合のいいように編纂された書物だったということか。
何回か前の記事で、蘇我氏の帝紀「天皇記」が蘇我倉山田石川麻呂の死後、「よき書」として中大兄皇子の手に渡った可能性をみたが、中大兄皇子(天智天皇)の寵臣といえば、中臣鎌足。
「天皇記」は中大兄皇子から鎌足に、鎌足から息子の不比等にと渡っていったのだとしたら、今回読んだ『古事記外伝』の主張も十分あり得る話になると思う。

「出雲国造神賀詞」のストーリー
蛇足になるが『古事記外伝』への個人的な感想を一点。
藤原・中臣氏に都合よく書き換えられた古事記のストーリーと、その現実世界での裏付けとして創建された「杵築大社(出雲大社)」———というところまでは藤巻さんの説に強く共感できるんだが、そこに「古事記が下敷きになってると思われる神賀詞の奏上」を加えて3点セットにすることにはチト同意できない。
『出雲国造神賀詞』は、奈良平安の出雲国造が代替わりする際、一族を率いて大挙上洛し、天皇の「御寿の長久と回春」を祝った祝詞のことで、716年の出雲果安のときは、神祇官の副長官「大副」を勤めていた中臣人足(ひとたり)に奏上すると、それを人足が天皇に復奏するという面倒くさい形式だったと『古事記外伝』に書いてある。
んでぼくが気になるのが、『神賀詞』で国造が述べる「国譲り」は、「タカミムスビ」の命令でアメノホヒが国見をし、その子ヒナドリに「フツヌシ」を副将につけてオオナモチを説得するストーリーになっていて、これだと日本書紀の本文(正伝)を出雲側に都合よく改変しただけのもので、伊勢神宮のアマテラスが藤原の氏神タケミカヅチを使者にするという古事記のストーリーとは異なってしまう。
しかもそんな内容を中臣氏の人足が天皇に復奏して平気でいるわけで、藤巻さんのいわれる「新秩序のシンボル」に『出雲国造神賀詞』を混ぜるのは、少々正確さに欠けてしまうような印象がぼくにはある。
古事記と日本書紀(11)につづく



