『史記』の徐福と安曇族
海洋学の専門家、亀山勝さんの『安曇族と徐福』(2009年)によれば、始皇帝の命令で不老不死の霊薬を探しに出かけた「徐福」は、安曇族の案内で日本の九州に渡ったのだという。
安曇族は春秋時代のBC473年に「越」に滅ぼされた「呉」の遺民で、福岡県の「志賀島」を拠点に大陸との交易を続け、日本に弥生文化をもたらしたという海洋民の集団だ。
有名な徐福は、山東半島にあった「斉」出身の「方士(道士)」。
亀山さんによれば、方士とは「宗教・医学・薬学・工学・化学(錬金術・煉丹術)といった幅広い知識と技術」をもつ人たちのことで、徐福も不老不死の仙薬の存在を始皇帝にプレゼンして、多額の援助をゲットしている。
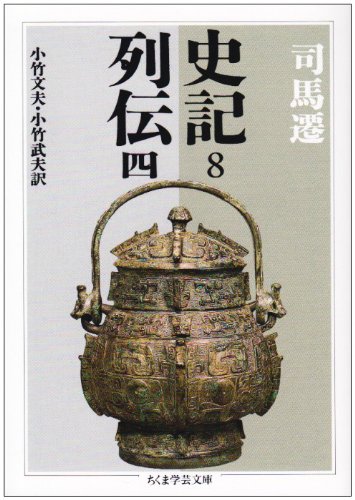
『史記』には徐福の記事が5ヶ所あるが、ストーリーとしてまとまってるのが「淮南衡山列伝」だ。
また徐福をつかわし、東海に入って神仙・不死の薬を捜させましたが、帰還していつわりごとを申し、『わたくしは海中の大神に会った』と言いました。大神が『おまえは西の皇帝(始皇)の使者か』と問うので、『そうです」と答え、『おまえはなにを求めているのか』と問うと、『延年長寿の薬を得たいのです』と答えた。
神は『おまえの秦王の礼物が手厚くないから、見せてつかわすが取ることは許さぬ』と言い、ただちに彼を従えて東南のかた蓬莱山に行き、霊芝(瑞草)の生えている宮殿を見せてくれたというのです。
そこには使者がおり、銅色で竜の形をし、光がさしのぼって天を照らしていました。
そこで彼は再拝して、『いかなる礼物を持参して献上すればよろしいか』と問うと、海神は『良家の男子、良家の女子および百工を献ずれば、得られよう』と言ったと申しました。秦の皇帝はすこぶる喜んで良家の男女三千人を遣わし、五穀の種と百工を携行させました。徐福は平原・大沢を手に入れ、そこにとどまって王となり、帰らなかったのです。
(淮南衡山列伝『史記 列伝』ちくま学芸文庫)
亀山さんによれば、まず徐福が東海であったという「海中の大神」は、安曇族のことだろうとのこと。そして徐福はBC219年に、大神=安曇族が要求した「良家の男女三千人」「五穀の種」「百工」を持参して、入植地の「平原・大沢」を紹介され、そこの「王」になったのだろうと。
『史記』の「秦始皇本紀」にはBC219年以後のこととして、BC212年に帰還しない徐福に怒った始皇帝が方士460人を生き埋めにしたとか、BC210年に方士たちが「大鮫魚(サメ)」が邪魔して仙薬が手に入らないと言い訳したとか、徐福と関連した記事を載せているが、亀山さんはそれらは山東半島に残っていた徐福の同業者たちの言動であって、徐福自身はBC219年に渡海した後は、ずっと日本で暮らしたのだろうと書かれている。

『三国志』と『後漢書』の徐福
徐福が渡来してから400年以上経ったAD230年には、三国志の「孫権」が、部下に徐福が渡ったという「亶洲(たんしゅう)」を捜索させている。
230年、(孫権は)将軍の衛温と諸葛直とを派遣し、武装兵一万を率いて海を渡り、夷州と亶洲とを捜させた。
(呉書『正史 三国志』ちくま学芸文庫)
亶洲は大海の中にあって、老人たちがいい伝えるところでは、秦の始皇帝が方士の徐福を遣わし、童子と童女と数千人を引きつれて海を渡り、蓬莱の神山とそこにある仙薬とを捜させたとき、徐福たちはこの島に留まって帰ってこなかった。
その子孫が代々伝わって数万戸にもなり、その洲に住む者がときどき会稽にやって来て布を商っていったり、会稽郡東部の諸県に住む者が、大風に遭って漂流し、亶洲に着く場合もあるという。
しかしこの洲は遥かな遠方にあって、衛温たちは、結局、それを捜しあてることができず、ただ夷州から数千人の住民をつれ帰っただけであった。
呉書のなかの「夷洲(いしゅう)」は台湾というのが定説なので、諸葛直らは台湾から数千人の住民を連行してきたものの、「亶洲(たんしゅう)」には行けていない。
その亶洲に住むという徐福の子孫は「数万戸」ということなので、沖縄や奄美、済州島とは考えにくく、九州のどこかの平野が妥当だろう。ちなみに魏志倭人伝にでてくる福岡平野の「奴国」は、人口二万戸と記されている。
5世紀に成立した『後漢書』の東夷列伝「倭」にも、徐福への言及がある。どうやらこの当時の人達には、徐福は「倭」に渡ったというコンセンサスがあったようだ。
また、夷洲および澶洲も会稽の海の彼方にある。
(倭「後漢書」『倭国伝』講談社学術文庫)
そこは、秦の始皇帝が、神仙方術家の徐福を派遣し、幼い男女数千人を率いて海上に出、蓬莱の仙人を捜させたが、仙人に会うことが出来ず、徐福は罰せられることを恐れて帰国せず、この澶洲に止まった。
その子孫は次々と増えて、数万家になったと伝えられる。その夷州や澶洲の人々はときたま会稽の市に来る。
というわけで、中国の文献によるなら徐福の行き先は「倭」ということになるが、考古学からも一点。
邪馬台国の時代に繁栄した佐賀県の「吉野ヶ里遺跡」で見つかった墳丘墓には、南側に祭祀遺跡、西南の方角に墓道、という組み合わせのものがあるが、これは漢の武帝が泰山の麓で行った「明堂の祀り」と一致したものなんだそうだ。
そんな儀式を熟知しているのは中国出身の「方士(道士)」しか考えられないので、徐福の「後継者」が関与した可能性があると、亀山さんはおっしゃるわけだ。
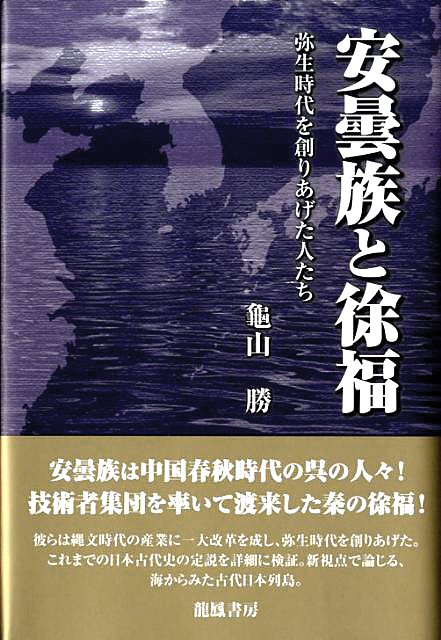
徐福は「有明海」北部に定着した
んで話はそこから広がっていって、そんな吉野ヶ里遺跡のある「佐賀平野」こそ、徐福が安曇族に導かれて定着した「平原・大沢」だったんじゃないか、というのが亀山さんの説。
先に、イメージを固めるために徐福一行の実数について触れておくと、まず問題になるのは食糧問題で、受け入れ側の安曇族の用意にも限界があるので「数千人」はさすがに無理。
せいぜい船は2〜3隻程度で、前漢時代の文献に載る「呉」の最大船員90人から考えて、「百工」の技術者は40〜60人、「少年少女」は130〜195人というのが亀山さんの推定値だ。亀山さんは海洋学の専門家なので、ここらの数字は信頼できると思う。
で、それぐらいの人数が渡来してきたわけだが、安曇族としては徐福と結んだ「契約」が履行されるべく監督・監視したいので、志賀島から近い場所がいい。これは食料や物資の輸送にも同様で、できるだけ行き来しやすい場所がいい。
すると実は弥生時代の福岡県には、今の大宰府のあたりで北へ向かう「御笠川」と南に向かう「宝満川(筑後川支流)」がめっちゃ接近する地点があって、博多湾と有明海は船で行き来できたのだという。

それに、当時の海岸線だと有明海のごく近くに鎮座していたことになる「風浪宮」(大川市)という神社は、阿曇磯良を祀る安曇族の氏神のひとつで、長野の「穂高神社」や愛知の「綿神社」と同様に、商社や農協・漁協の機能を持つ「(株)安曇海運の支社」だと考えられるのだという。
また有明海は、当時の最先端技術「V字型船底」の帆船を造るのに適した「潮の干満差(潮位差)」が6メートルもあって、日本一!という利点もある。
干潮時に堤防をつくって満潮時でも海水が入らない場所で船をつくり、完成したら堤防を切って海水に船を浮かべる———という「ドライドック」に最適で、この一点だけで徐福の定着地だと主張している中国人の研究者もいるそうだ。

というわけで、『史記』がいう「平原・大沢」という地形、吉野ヶ里の祭祀遺跡、造船に有利な潮位差、博多湾と有明海を結ぶ水路の存在、風浪宮の鎮座・・・などを考慮すると、有明海北部(佐賀市、大川市、柳川市)あたりが徐福一行の定着地の可能性が高い———というのが、亀山さんの結論だ。
徐福の墓は吉武高木遺跡か

もちろん、海のシロートであるぼくに異論があるはずもないんだが、ちょっち気になるのが「V字型船底」の高速帆船を欲しがってるのは安曇族であって、徐福ではない点。
徐福は単純に「平原・大沢」の「王」になりたかったわけで、そうすると候補の一つに上がりそうなのが「最古の王墓」が見つかっている福岡市西区の「吉武高木遺跡」だろう。
丁度、徐福の一行が渡来したBC219年に近いBC200年頃から大発展したといわれる弥生ムラで、最盛期の総面積は40haとなかなかの規模だ。

吉武高木遺跡は、ロケーション的にはのちの「伊都国」と「奴国」の間の早良平野に陣取っていて、安曇族の志賀島とは博多湾を挟んで向かい合ってる状況。監視するには程よい距離だ。近くには「室見川」という立派な川も流れているので、船での行き来も容易いこと。
面白いことに、吉武高木の近隣にある「有田遺跡」からは、安曇族が中国から伝えたという「養蚕技術」から作られた国産の「絹」、その最古のものが出土してるのだという。

それと吉武高木遺跡では何と言っても有名なのが「三号木棺墓」で、なんと「鏡」「剣」「玉」の三種の神器が揃って出土している。こいつが人呼んで「日本最古の王墓」で、出てきた銅鏡(多鈕細文鏡)は中国東北地方に源流があるものだという。
まぁ「王墓」とはいってもまだまだ「特定個人墓」のレベルには達してなくて、吉武高木では比較的大型で豪華な副葬品をもつ「木棺墓」と「甕棺墓」が20基ほど、集中して埋葬されている状態(特定集団墓)。
吉武高木ではそうした上級国民の集団墓が100年ほど造営されたあと、地元で「甕棺ロード」といわれる丘陵地帯に、副葬品のグレードを落とした墓が200基、副葬品をなにも持たない墓が1000基以上、乱雑に埋葬されていったようだが、この期間のもろもろの流れはよく分かっていないらしい。
でぼくとしては、安曇族に都合の良いロケーションと、ちょうど徐福一行の年配者(百工?)が亡くなるBC200年ごろからの墓地造営のタイミングから、吉武高木を徐福の定着地の候補に上げたいわけだが、論拠に乏しい印象論であることは自覚している。
難しいことに、BC100年頃からは、吉武高木からリーダーと特定できる大型墓が見当たらなくなる一方で、弥生時代としては最大級となる面積182㎡(畳112枚)の大型建物が建造されたりもして、だが結局は隣りの「伊都国」や「奴国」のような「クニ」には発達しなかったという、その全ての理由がぜんぜん分からないことばかりらしい。
※詳しいことは、福岡市の公式サイトを御覧ください(「吉武高木遺跡とは?」)。
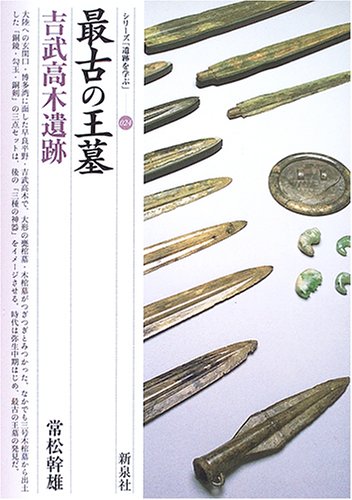
最後に、吉武高木遺跡の発掘を担当された考古学者、常松幹雄さんの著書『最古の王墓 吉武高木遺跡』(2014年)から、ぼくが面白いと思った話をつまんでみる。
まず弥生時代の北部九州では、「銅矛」の付け根に「耳」といわれる半円のリングを付けていたり、柄を差し込むソケットの根元に「節帯」といわれる輪を鋳出していたりするが、それらは朝鮮半島では見られないもので「まだわかっていない青銅器工人集団の系譜」が考えられるという。
また、吉武高木からは実用性のない扁平な「銅戈(どうか)」が出土しているが、これも朝鮮半島では見られないもので「初期の段階から祭器的な性格を持つ青銅の武器」が存在していた、ともいう。
ということで常松さんは、一般的にいわれるように青銅器の鋳造などの先端技術が朝鮮半島からもたらされたことを熟知しつつ、それとは別のルートやルーツがあることを吉武高木の遺物から感じ取られているようだ。
こうした技術導入の背景には渡来系集団が介在したと推察される。
しかし、朝鮮半島にみられるような、細形銅剣単独の副葬から銅矛・銅文が加わる副葬へ移行するような過程は北部九州では認められない。有文青銅器や小銅鐸など副葬品の組成が酷似する墓も存在しない。また、吉武高木の中核墓の甕棺墓は、弥生前期後葉から発達した大型化をきわめた土器棺を組み合わせたものだ。木棺墓にともなうヒスイの勾玉にも、縄文時代的な特徴がみられる。
これは吉武高木の墓制や装身具の構成が、突如としてあらわれたものではなく、弥生前期の文化を土台に成立したことを示している。『漢書地理志』に登場する「百余国」の原形は、中期前半までに確立された、といえよう。
(『最古の王墓 吉武高木遺跡』)
常松さんはそれを、縄文時代から続くわが国特有の文化に求めているが、ぼくには何となく、徐福の一行が持ち込んだものもあるのかなーという印象がある(むろん個人の感想)。
それにしても分からないのは、徐福が連れてきて「百工」の技術を覚えさせたと思われる少年少女のその後の行方・・・。多く見積もって200人という彼らは徐福の死後、一体どこで何をしていたんだろう。
神武天皇(4)につづく



